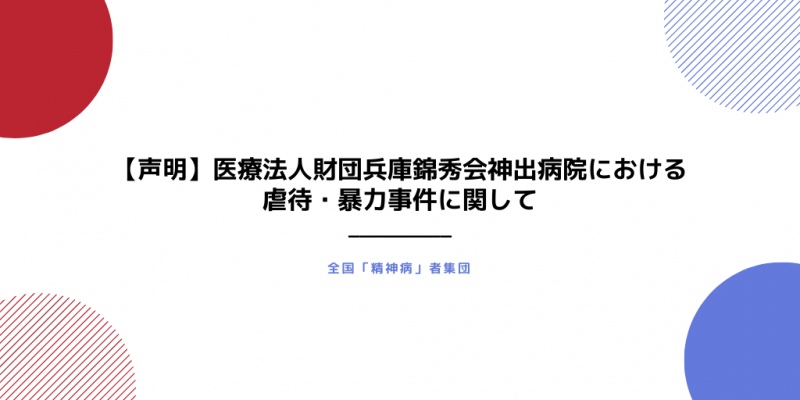厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 殿
同 企画課長 殿
同 障害福祉課長 殿
同 精神障害保健課長 殿
日ごろより障害者の地域生活の推進にご尽力くださり心より敬意を表しております。
さて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の見直しの時期が近づいてまいりました。
同法の見直しが附帯決議及び障害者の権利に関する条約(以下、「障害者権利条約」とする。)の趣旨を鑑みたものとなるように下記の通り、要望を申し上げます。
記
1.検討
1)障害者団体の参画について
障害者権利条約第4条第3項では、障害者に関する問題について政策決定過程から障害者を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させることとされています。よって、同法の見直しの検討には、私たち全国「精神病」者集団を含め障害者団体の参画を保障してください。また、ヒアリングも例年通り実施してください。
2)精神障害者の参画について
障害者基本計画(第4次)では、障害者施策を審議する国の審議会等における障害者の委員については、障害種別及び性別にも配慮して選任を行うこととされています。
また、参議院附帯決議では、施行後三年の見直しの議論に当たっては、障害者の権利に関する条約の理念に基づき、障害種別を踏まえた当事者の参画を十分に確保することとされています。同法第4条第1項において精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)とされています。ピアサポーターの職能団体の参画は一定進んでいるものの、地域患者会や病棟患者自治会、自立生活センタースタッフなど幅広い層の精神障害者を構成員とした全国組織から推薦を得た精神障害当事者の参画が不十分です。ピアサポーターの職能団体の代表者だけではなく、地域患者会や病棟患者自治会、自立生活センタースタッフなど幅広い層の精神障害者を構成員とした全国組織から推薦を得た精神障害当事者の参画こそ優先して進めてください。
3)報酬改訂の検討における当事者参画
訪問系サービスの処遇改善加算率見直し、基本報酬の改訂について私たち全国「精神病」者集団を含め利用者である当事者の団体の検討段階からの参画を保障してください。
2.総則
同法第7条に規定された介護保険優先原則は撤廃してください。同法は、障害者の自立生活のための法律であり、介護保険とは本質的に異なるものです。よって、同法のサービスを介護保険のサービスに相当すると見なさないでください。
3.障害支援区分認定と支給決定
障害支援区分認定調査のアセスメントは障害程度区分認定調査から大幅に改善されたが、それでも精神障害者の支援区分が低く出るきらいが否めません。そのため、障害支援区分認定調査のアセスメント又はマニュアルは、さらに見直してください。
現在の支給決定方式は、二次審査のための意見書を精神科医が書くなど医学モデルに依拠しています。将来的には、現在の支給決定の方式を改め、社会モデルの観点からニーズを中心とした協議調整モデルに改めてください。
市区町村によっては、相談支援専門員のサービス等利用計画案よりも低い支給量しかでないことがあるが、もっとサービス等利用計画が尊重されるようにしてください。
障害程度区分認定調査員は、意思決定支援ガイドラインの拘束をうけないが、技能に不均等が認められます。意思決定支援や合理的配慮義務、マニュアルの遵守ほかを徹底するようにしてください。
4.居宅介護
1)育児支援
支給決定する市区町村が居宅介護の業務に含まれる育児支援の存在を知らないがゆえに育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障害者である場合の育児支援に対して支給しないケースが散見されます。育児支援の周知が不十分であるため、あらためて地方公共団体に向けて文書で周知徹底を図ってください。また、育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障害者であるにもかかわらず、障害者を支援する責務をもった地方公共団体が支援をせずに結果としてネグレクト状態に陥り、児童相談所が一時保護をするケースが散見されます。これについては、障害者行政と児童行政の連携に瑕疵があると言わざるを得ません。
2)通院等介助の自宅発着条件
通院等介助は、自宅発着条件を削除してください。また、勤務先から通院先までの移動にも使えるようにしてください。
5.重度訪問介護
1)障害支援区分と行動障害点数
重度訪問介護は、長期入院者等の退院後の地域生活の資源としてきわめて重要です。しかし、多くの精神障害者は、障害支援区分4以上・行動障害10点以上が出ないためニーズがあっても重度訪問介護の利用ができません。行動障害10点の撤廃と支援区分4以下への適用拡大をしてください。また、入院中の重度訪問介護の利用についても支援区分4及び5に適用拡大してください。
2)通勤、勤務中等の利用
重度訪問介護は、通勤、勤務中、通学、修学中の利用を認めるべきです。重度訪問介護の移動制限である「通年かつ長期にわたる外出」を削除すべきです。
3)重度訪問介護従業者養成研修行動障害課程
重度訪問介護従業者養成研修行動障害課程ができたことを評価しています。但し、精神中心と知的中心で運用に若干の差異を認めるため、利用が促進されるように研修の事例集積をおこなうなどしてベストプラクティスを示してください。
4)3人以上の介護
介助内容によっては、2人介護では不十分な場合があるため、3人以上の介護でも支給をできるようにしてください。
6.自立生活援助
自立生活援助の支給期間が一律3年なのは個別性を無視したものです。ニーズに応じて個別的に期限を決定できるようにしてください。
7.共同生活援助
1)運用の実態把握の必要性
共同生活援助事業者の提供するサービスにはバラツキがあります。あからさまなネグレクト運営がある一方、外出制限等の過度な干渉をする事業者など問題のある例が散見されます。共同生活援助の実態調査をしてください。
2)大規模型について
定員20人以上の大規模型共同生活援助は報酬から削除してください。
8.就労継続支援A型及び就労継続支援B型
1)合理的配慮の不徹底
就労継続支援A型事業における合理的配慮の不徹底が散見されるため必要な措置を講じてください。
2)工賃額と報酬
前回の報酬改訂では、工賃額によって報酬が変わる仕組みが採用されました。しかし、この報酬体系はインセンティブを与えるどころか、単純に居心地が悪くなっただけでした。精神障害者には、休息が必要な人が多いため、就労支援機能と居場所機能が共存してはじめて支援となる場合が多いです。工賃と報酬を連動させるべきではないし、就労支援機能と居場所機能の双方が認められるような仕組みにしてください。
3)就労目標
就労を目標とした制度には限界があります。居場所機能の価値を認めてください。
9.相談支援事業
1)相談支援事業所と相談支援専門員の不足
相談支援事業所と相談支援専門員の数が不足しています。そのため、サービス等利用計画が供給できていません。地域によっては、サービス自体が使えないような状態となっています。また、セルフプランの位置付けが弱いことも問題です。相談支援は、報酬額が低いため基本報酬の拡充と加算を充実してください。
2)利用契約と支給決定
計画相談の支給決定は、利用契約と支給決定が連動しています。しかし、契約解除をしていないのに支給決定が変更されているケースがあります。市区町村が利用者と事業者の契約関係を確認せずに支給決定を変更したためと思われますが、混乱が著しいため改めて文書で注意を促してください。
3)初任研修及び現任研修
初任研修及び現任研修の改訂は評価しています。医学モデルに基づくソーシャルワークに依拠した説明を脱し、社会モデルに基づく研修にしてください。
10.地域移行・定着
1)地域移行・地域定着の機能強化
地域移行・地域定着はあまり機能していません。機能するように見直してください。また、患者等にも知られてないため精神科病院内でも入院患者に周知をしてください。
2)精神科病院の面会制限の非適用
地域相談をおこなう相談支援専門員の面会制限を非適用にしてください。
11.地域生活支援事業
1)移動支援
移動支援の地域格差を解消してください。
2)アサポーター研修
アサポーター研修の想定するピアサポーターは事業所に雇われた精神障害者に限定されており、自立生活センタースタッフ、病棟患者自治会、地域患者会などのピアサポーターが想定されていません。また、当事者団体がピアサポーターの範囲に含まれていません。ピアサポーターの範囲を見直してください。
3)成年後見制度利用促進事業
国連は成年後見制度を条約違反としています。成年後見制度利用促進事業は、成年後見制度との関係から見直しが求められているはずであり、このまま運用を続けることはできないです。成年後見制度利用促進事業の運用を中止してください。
12.障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライン
国連障害者の権利に関する委員会は、一般的意見第1号において最善の利益を否定しています。そのため、最善の利益を規定した障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインは一般的意見を参考にしながら見直してください。
以 上