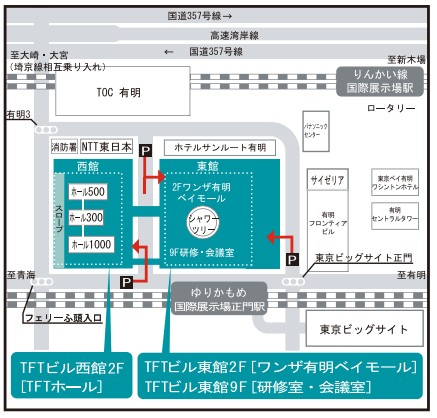ハンセン病に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会
ハンセン病以外の患者団体等へのヒアリング意見書
0 全国「精神病」者集団の活動紹介
1974年5月に結成した精神障害者の個人及び団体で構成される全国組織である。世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワークという精神障害者の世界組織に加盟している。主に精神障害者同士の互助を中心とした活動の連絡と実践をしてきた。結成当初から精神保健福祉法の非自発的入院や精神障害者と犯罪を結びつける刑法改正法案処分に対して反対の立場を示し、差別や偏見の克服のためにさまざまな取り組みをしてきた。
1 報告書に示された内容からみて、当事者、国あるいは自治体、医療の現場などは、どういう状態にあると捉えておられますか。また、現状分析とあわせ、平成21年度ヒアリング以降の社会環境の変遷についてどう捉えているか(前進したこと、後退したこと、変わらないこと)についても触れていただけると幸いです。
【総論】
報告書の「患者の権利に関する体系」の趣旨に従い、平成21年度ヒアリング以降の社会環境の変遷を踏まえつつ当事者、国あるいは自治体、医療の現場の状態を述べる。
1.1 障害者権利条約の批准
精神障害者の場合は、医療にかかった患者がすなわち精神障害者になりうる(精神保健福祉法第5条)。精神障害者は、障害者基本法に基づく障害者であり、障害者に係る全ての政策は、障害者権利条約の趣旨を踏まえた検討をしなければならない。2009年に「ハンセン病に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会報告書」(以下、報告書)が出された段階では、障害者権利条約は批准されていなかった。しかし、2013年12月に日本政府は障害者権利条約に批准し、現在では締約国として障害者権利条約の趣旨に則した政策の検討が不可欠となっている。この点で国の状態は大きな変遷をとげている。
2013年の段階で日本政府は、精神保健福祉法の非自発的入院が障害のみを理由として非自発的入院させる制度ではないため、障害者権利条約に違反しないとする解釈に基づき批准を決めた。しかし、2014年4月に採択された障害者権利委員会一般的意見第1号、2015年9月に採択された同委員会14条ガイドラインなどで精神保健福祉法を名指して障害と追加の要件で非自発的入院させる制度であっても障害者権利条約に違反するとの公式な見解が示された。このことで2020年以降に予定されている障害者権利条約政府審査では、総括所見で精神保健福祉法の非自発的入院制度の廃止が勧告される見込みである。そう遠くない将来に勧告を受けることが確実ならば、それを見越して、既に通説となっている精神障害を要件とした非自発的入院は障害者権利条約第12条、同条約第14条ほかに違反するという前提に立って、精神保健福祉法の非自発的入院及び行動制限の廃止について医療基本法の枠内でも検討されなければならない。
1.2 精神医療
精神科医療は入院医療中心である。それは、入院でなければできない医療が中心だからというわけではなく、精神科病院全体の7割を占める民間病院の経営を第一義的な目的においた政策の帰結としてそうなっている。入院は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき自発的入院と非自発的入院と大別される。入院(とくに非自発的入院)は、純粋に医療的な要請でおこなわれるものばかりではなく、社会防衛的な要請による入院など非自発的入院の濫用なども非常に多く散見される。例えば、家族内のトラブルを理由とした入院のようなものまである。非自発的入院は、基本的に人権侵害であり、仮に医療上の必要があるとしても、医療不信を帰結し治療関係の継続を困難せしめる。
大部分の精神疾患の原因は、不明とされている。そのため、様々な仮説があるものの根本治療の確立には至っていない。投薬治療をはじめとする精神科医療における治療のほとんどが対症療法である。もっとも普及している治療法は投薬治療である。向精神薬の投薬治療は、薬物投与の中では比較的侵襲性が高い治療法である。投薬治療は、薬効の個人差が非常に大きく、ほとんどが身体の動きを鈍くするだけの作用しかもたないため、効果を示す人よりも効果を示さない人の方が多いといわれている。そのわりには、副作用被害が大きく、不可逆的な後遺症を残す人もきわめて多い。向精神薬の多くは、治験データなどが非公開とされており、患者が根拠を知るすべをもたない。
さらに侵襲性の高い介入として電気痙攣療法(ECT)と呼ばれる側頭部に電極をあてて通電する治療法がある。ECTも投薬治療と同様で科学的根拠に乏しい。ECTは、通電後に痙攣するさまから患者及び家族から恐れられており、記憶障害などの後遺症の報告も後を絶たない。最近では、従来の電気痙攣療法と異なり、麻酔を使用して痙攣させないことやサイン波からパルス波にかわったことで副作用が軽減されたとする医学書の解説が散見されるが、パルス波であっても侵襲性が高いことにかわりはなく、副作用の報告も非常に多い。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下、医療観察法)においては、目的条項に「病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り」とあり、犯罪の防止のために医療を使うことが示されている。
これらは総じて患者・医療者間の信頼関係を壊し、医療不信をもたらしている点で、国、自治体、医療の現場全体が報告書の理念と比較して2009年から後退したものと判断した。
【各論】
報告書の「患者の権利に関する体系」の箇条書きに従って各論の意見を述べる。
1.3 医療の理念
Ⅰ-1-1「医療の理念」及びⅡ-2-4「治療に対する同意と拒否」については、後退していると判断する。理由は、2009年から現在まで数回にわたって尊厳死立法が上程されかけたからである。尊厳死は、表向きは尊厳に基づく生/死の決定とされているが、その実は純粋に生き死を等価に論じているわけではなく、疾病のない生と疾病のある生とを比べて疾病のある生を否定したいがために死を選択できるようにと論じたものである。これは差別であり、報告書の趣旨である患者の権利や生命の尊厳に悖る。こうした差別を治療同意における拒否権の文脈のみを取り出して正当化する立場もあるが、報告書の趣旨とは相いれない。
1.4 医療政策立案などへの参加
Ⅰ-1-5「医療政策立案などへの参加」については、後退していると判断する。障害者政策委員会からは、もともと構成員として入っていた精神障害者が構成員からはずされ、その後、今日まで精神障害者が構成員としてメンバーに入れられてこなかった。
精神保健福祉法の見直しの検討をおこなってきた「これからの精神保健医療福祉のあり方検討会」(以下、あり方検討会)では、精神障害者団体から推薦を受けた精神障害者はおらず、団体の推薦を受けていない精神障害者が2人だけであり、構成員全体から見て非常に少ない。また、あり方検討会において精神障害者の構成員の意見はほとんど反映されていない。
成年後見制度利用促進委員会では、精神障害者団体から推薦を受けた精神障害者はおらず、職能団体から推薦をうけた精神障害者が1人だけであった。
1.5 疾病障害による差別の禁止
Ⅰ-1-6「疾病障害による差別の禁止」については、変わらないと判断する。2016年4月から障害者差別解消法が施行されたが、民間事業者等は合理的配慮の提供が努力義務の域に留まる。精神科病院の7割は私立病院であり、私立病院による差別の禁止が努力義務の域にとどまる点で、多くの精神障害者にとって実態に大きな変化が与えられたとまではいえない。
1.6 患者の自己決定権
Ⅱ-2-1「患者の自己決定権」については、後退していると判断する。成年後見制度利用促進計画において成年後見人の業務の範囲に医療同意の代理を含めようとする議論があり、患者の自己決定権への配慮がない施策が十分な検討を経ずに進められてしまっている。
また、精神保健福祉法の非自発的入院及び行動制限は、医療政策立案過程である「あり方検討会」において精神障害当事者から廃止すべきとの意見が出されたが、患者の自己決定権への配慮がない施策が十分な検討を経ずに進められてしまっている。
1.7 本人の同意によらない医療、措置
Ⅱ-2-2「本人の同意によらない医療、措置」については、後退していると判断する。精神障害者に対して特別に本人の同意によらない入院等を定めた精神保健福祉法は改められるべきである。改められるにあたっては、緊急避難法理を念頭においたものとして再編されることが必要である。しかし、精神保健福祉法の同意のあり方をめぐっては、一切の検討がなされないまま存続している点で問題がある。
非自発的入院は、基本的に人権侵害であり、仮に医療上の必要があるとしても、医療不信を帰結し治療関係の継続を困難せしめる。そして、患者・医療者間の信頼関係を壊し、医療不信をもたらしている。
1.8 プライバシー及び診療情報を知らされない権利
Ⅱ-1-1「患者の尊厳とプライバシー」及びⅡ-3-4「診療情報を知らされない権利」については、後退していると判断する。2017年2月に上程された精神保健福祉法改正案では、措置入院者全員に退院後支援計画を定めることとされ、計画策定のための個別ケース検討会議には援助関係者として警察が入ることとされた。現在は、廃案となっているが、再び同じ内容の法案が2018年の通常国会に上程される見込みである。支援計画自体は、作成が必須とされており、個人の病歴や家族歴などを行政側が把握し、援助関係者の間で共有されることになる。ここに警察が入ることが想定されているが警察が取得した情報については、治安・監視目的の利用を妨げない。もちろん、これまでも精神障害者の地域生活支援のために情報共有がおこなわれてはきたが、これとてプライバシーの主体である患者本人の同意が前提としてあったはずである。当該法案における退院後支援計画は、そもそも入院に同意をしていない措置入院者を対象として、更に本人の同意がなくても一律作成され、警察を含む広い範囲で共有されることが前提とされている点でプライバシーの観点からも大きな問題がある。こうした場合、精神障害者は、医療者に伝えた情報が警察に伝わることを恐れて、医療に対して自分のことを語らなくなり、医療者との信頼関係を根本から崩してしまうことにつながる。
2 報告書の内容と現場の実態に乖離した部分があれば、その具体的内容についてご教示ください。
2.1 基本的な理解
上述で後退と評価したものは、必然的に報告書と実態の乖離を帰結する。そのため、2.2以降は新たな論点を中心に述べたい。
2.2 身体拘束中に死亡したニュージーランド人:ケリー・サベジさんの事例
2017年4月30日、ケリー・サベジさんはA病院へと措置入院になった。兄のパットさんは、ケリーさんの診察に立ち合い、ケリーさんに通訳などのサポートをした。このときに兄は、ケリーさんが診察にきちんと応じているところを確認した。だが、精神保健指定医は、再び全裸で外出してしまうおそれがあるなどとして措置入院の決定を下した。そして、兄と警察、病院職員とでケリーさんを閉鎖病棟まで連れていき保護室のベッドに寝かせた。このときケリーさんは命令に従ってベッドに寝たのだが、それにもかかわらず病院職員は、ケリーさんに対して足、腰、手首の6点に身体拘束をした。兄は、病院のスタッフに「拘束する必要はないのではないか」と聞いたが、「しばらく拘束される」とだけ伝えられ、ちゃんとした説明もしてもらえなかった。
5月10日、病院の職員が身体拘束されたまま心配停止状態になっているケリーさんを発見した。なお、前日にケリーさんは、「このままでは死んでしまう」と訴えていたようである。病院は、心臓マッサージをしながらケリーさんを市内の総合病院に運んだ。再び心臓が動き出したが、意識と呼吸は戻らなかったため、そのまま人工呼吸器装着となった。総合病院の主治医は「推定ですが、10日間、抑制されていたことを考えると、いつから出来たかはわかりませんが、深部性脈血栓が発生し、肺塞栓に至り、心配停止となった可能性が考えられます」と診断した。17日、とうとう心臓が完全に止まり、家族は主治医と一緒に死亡の確認をした。
兄と母のマーサさんは、病院に対して「なぜケリーさんが死んでしまったのか」と説明を求めた。そして医師は、遺族らに対して、病理解剖の結果、心肺停止状態になった原因が見つけられなかったと説明した。遺族らは「なぜ血栓を見つけられなかったのか」と聞いたところ、医師は「血栓が比較的新しい場合、亡くなってから固くなった血との区別が難しい」と説明した。
7月12日、パットさん夫婦と支援者がカルテ開示のためにA病院に足を運んだ。A病院は、閲覧以外の方法を定めていない様式のカルテ開示請求書をわたし、カルテ開示では閲覧のみとして複写を拒絶した。それからは、複写を求めても「あなた自身が複写を請求していないため今日はできない」と繰り返し、あたかも遺族側に原因があるかのように主張した。また、カルテ閲覧もプロジェクターを使って映像で映し、病院職員が機械を操作して見せるかどうかを個別に判断するという方法であった。
病院側は、遺族らの質問に対して何度か意図的に答えなかった。そして、遺族らが代理人弁護士を付けたことで病院が答えられない状況を作っていると主張した。カルテには、兄が身体拘束に同意したと書かれていたが、兄は同意していないと強く主張した。その後、様々な働きかけを経て数カ月遅れでようやくカルテ開示(複写)が決まった。厚生労働省は、当該身体拘束において精神保健福祉法上の違反はなかったと公表した。
この事例では、本人および家族に十部な説明をしないまま身体拘束し、死後においても診療録開示などを不当に拒み延滞させるなど、報告書のⅡ-2-5「医療従事者の十分な説明」、Ⅱ-3-1「医療情報へのアクセス」、Ⅱ-3-2「診療記録などの開示請求権」、Ⅱ-3-3「医療従事者の診断内容の説明」に照らして、著しく実態が乖離している。本事例に限らず十分な説明を受けないままに身体拘束や非自発的入院になる患者は非常に多い。
また、こうした事例は、Ⅱ-7-2「患者の自由制限措置」とも関係しており、この身体拘束が果たして必要最低限のものであったのか、そもそも必要最低限とはどれくらいのもので、何を基準にして最低限といいうるのか、それは誰が判断するのか、など報告書の読み方とも関係してくるが、報告書の趣旨を踏まえるなら、患者の権利を帰結していない点で必要最低限とはいえず、実態が報告書と大きく乖離している。
3 その現状をふまえ、医療基本法の法制化に向けて、次のステップとして、具体的にどのような取り組みが必要と思われますか。
3.1 患者中心の検討
1で述べた2009年からの後退に歯止めをかけるためにも患者の目線による医療基本法の制定が不可欠と考える。医療基本法には、患者の権利に関する法規範を患者の視点で定める必要がある。もっとも望ましいのは、医療を計画的に提供するための基本法という供給側の論理に依拠した性格の法規範ではなく、医療を受ける患者の権利を患者目線で定めた法規範である。そのため、医療はなにを目的としたもので、どこまでを守備範囲とするのか、このことを医療基本法の中で定め、現状追認型の法規範ではなく、現状に変更を与えるための法規範になるよう患者中心の検討を丁寧におこなう必要がある。現状追認型の医療基本法は、ハンセン病問題に関する検証会議の提言や報告書の趣旨と異なると考える。すなわち、患者に対する権利侵害の実体に変更を与え得るような医療基本法でなければ意味がない。
具体的には、らい予防法のように患者の権利に資さない法規範については、医療基本法の中に医療の基本政策の見直しのための計画作成の規定を設けて、その計画に基づき国が改廃等の見直しの検討を進められるようにしていくなどが考えられる。
こうした規定を設けるためにも、立法過程は患者中心の検討でなければならず、まずは、厚生労働省、立法府及び与野党、両院議員は、患者中心の検討の場を設ける必要がある。
3.2 障害者権利条約に基づく検討
1で述べたとおり、障害者権利条約に基づく立法の検討が取りくまれる必要がある。
また、医療基本法の制定にあたっては、目的条項において障害者の患者に関しては障害者基本法と相まって施策を推進していく旨の理念を明文化する必要がある。
そうすることで障害者権利条約の趣旨に基づく障害者施策の実施との整合を図りながら患者の権利について検討していくことが可能になる。
3.3 患者主体の確認と医療従事者の責務の確認
報告書のⅡ-2-5、Ⅱ-3-3の書きぶりにみられるように主語を医療従事者とすることは、語法的に報告書の趣旨であるはずの患者主体が不明瞭にされてしまう。他方でⅡ-8-1は、患者の権利として「対応を求めることができる」とするよりも、医療従事者の責務として「求めに応じなければならない」と規定することで、より患者の権利を積極的に守るような書きぶりになる。このように患者に権利があることを確認するための規定と、患者の権利を守るために医療従事者が何を責務とするのかを明らかにするための規定との関係を整理することによって患者主体をより明確にしていくことができるので、これに取り組む必要がある。
3.4 患者の権利と相容れない制度の改廃
ケリー・サベジさんの事例は、身体拘束中に死亡した事例であるが、こうした死亡事例は比較的多く、当会も全国から相談を受けている。そのことからも比較的高い可能性で身体拘束が死を帰結するリスクを有しており、身体拘束をしないことに伴うリスクよりも身体拘束をするリスクの方が上回るため、特定の場合に限り(例えば障害を理由とした場合など)一律禁止されなければ患者の権利の実現は難しいと考える。
Ⅱ-5-1「自らの健康状況の自覚」との関係では、主に一般的な健康増進などが想定されていると思われるが、精神保健福祉法の非自発的入院を正当化するために用いられる病識概念との混同が避けられるよう報告書の趣旨の確認が重ねて求められるはずである。報告書の趣旨は、精神保健福祉法の運用のように健康状況の自覚がない者をかたっぱしから医療施設に収容することを患者の権利などと考えていないため、障害者権利条約の趣旨に従い精神障害に局限した医療同意能力の不平等を見直す必要がある。
また、Ⅱ-2-2「本人の同意によらない医療、措置」及びⅡ-7-3「適正手続」との関係では、主に緊急非難法理などが想定されていると思われるが、精神保健福祉法の非自発的入院及び行動制限制度のように精神障害者に限った特別な同意のない医療開始手続きを定めた制度との混同が避けられるよう報告書の趣旨の確認が重ねて求められるはずである。そうでなければ、手続きさえ守ればいかなる侵襲をおこない人権侵害をしてもいいとうことになりかねない。精神科病院による非自発的入院及び行動制限の運用実態は、補充性要件や法益権衡要件を満たさず、そもそも医療であるかさえ疑わしいものであるため、適正手続によって正当化され得るものではない。そのため、障害者権利条約の趣旨に従い障害を理由とした非自発的入院及び行動制限は、廃止される必要がある。医療基本法の制定に向けては、権利侵害の法典を確認する作業が次のステップとして取り組む必要がある。
3.5 行動制限等の廃止による制度の移行措置
精神科病院に限らず病院では、医療従事者の権限が大きく作用する。にもかかわらず、患者の権利は法典において明文で十分な位置付けを得られていない。そうした中で、精神科医療は、精神保健福祉法の37条1項の大臣基準と実地指導体制のようなものを設けて運用してきた。換言すれば一般医療では、隔離・拘束の基準が設けられておらず、実地指導も義務付けられていない。医療全般の状況から鑑みても実態をコントロールするための手続きは必要である。しかし、それは精神保健福祉法ではない法律によって裏付けられる必要がある。精神保健福祉法のように供給側の視点からではなく、患者側の視点から患者の権利の法規範に基づき医療提供状況の監視体制が裏付けられていくべきである。医療基本法の制定に向けては、まずは既存制度のなにを残し、なにを廃止すべきかを確認する作業に取り組む必要がある。
3.6 行政改革
精神障害者の場合は、厚生労働省設置法の見直しといった行政改革を含む抜本的な見直しが不可欠となる。「すべての人の身体的精神的な到達しうる最高水準の健康の享受の権利に関する特別報告者報告」(A/HRC/35/21 2017年3月28日)には、精神保健サービスが特別な枠組みによらず一般の地域保健サービスの一部として展開されるべきであると示されている(para,54,55,56)。精神障害に特化した行政は、供給側の政治的要請に影響を受けやすい点で問題がある。そのため、精神科医療を一般医療に、精神保健を一般地域保健に、精神障害者福祉を障害者福祉に振り分ける必要がある。その上では、精神障害保健課という部署を解体し、医療は医政局、保健は健康局、福祉は社会・援護局へと分散していく行政改革が必要になる。
4 医療基本法の法制化にあたり、障害となる要因はありますか。あるとすれば、その具体的内容をご教示ください。
4.1 供給側の視角のみで制定され患者の視点が反映されない可能性
医療基本法は、医療の計画的な供給のための法規範に留めようとする医療提供側の政治的要請がある。ここうした動きは、現状追認型の医療基本法を帰結する点で問題があり、医療基本法の制定にあたって最も大きな障害となる。現状に変更を与えるための医療基本法にするためには、患者の権利に基づいた医療基本政策の見直しのための計画策定を条文に定めたものでなければならない。その計画に基づいて、かつてのらい予防法のような法律(例えば、精神保健福祉法)を廃止し、患者の権利のための新たな仕組みに変更していくことが求められる。
4.2 患者の権利に資さない法典の存在
上述のとおり、精神保健福祉法の非自発的入院及び行動制限は、権利について定めた障害者権利条約に違反することが指摘されている。このことから精神保健福祉法自体がらい予防法と同様で患者の権利に資さない法典であることがわかる。こうした法典は、患者の権利の観点から見直されなければならない。仮に、見直しがなされないまま見切り発車的に医療基本法が制定されても患者の権利が守られないことになる。また、そうした場合には、患者たちから医療基本法の制定への否定的な見方が広まり、医療基本法の制定の障害になり得る。
4.3 医療計画における基準病床値及び治療影響値
このたびの医療計画は、医療基本法制定の契機として非常に大きな意義を有している。医療計画は、医療の計画的な供給を定めたものであり、供給体制の指標を定めた医療基本政策の核をなす計画に相当するものである。
他方で医療計画の中身については、いくつか看過できない問題を孕んでいるため、医療基本法の制定に先駆けて解消される必要がある。
このたびの医療計画では、基準病床値(係数a)の設定方法として1年以上入院している長期在院者の約7割が「重度かつ慢性」者という長期入院の需要がある者とされ病床削減もされないこととなった。また、治療影響値(係数b)は、侵襲性の高いmECTとクロザピン治療の計画的普及によって「重度かつ慢性」者の退院が進むこととされており、医療政策の考え方から方法に至るまで問題が大きい。この計画に多くの精神障害者が怯えている。このような計画のままでは、患者と医療従事者の信頼関係の構築も難しく医療基本法の制定の障害にさえなりうるため、解消される必要がある。
5 医療基本法の法制化が進んだ場合、実際に、医療の現場(患者の生活)にどのような影響がある、あるいはどのような変化が起きると思われますか。
5.1 長期在院者の問題の解消
日本の病床約125万床の内、精神病床は約35万床で全体の4分の1を占める。全精神病床入院者の内、3分の1程度は1年以上の長期入院者とされている。長期在院の解消は、国も取り組むべき課題と認めて、精神保健医療福祉改革ビジョン(2004年)において受入環境があれば退院できる社会的入院患者が約7万2千人いるとされ解消が目指された。ただ、長期在院の解消はあまり進まず、今日までで約2万人程度しか達成されていない。片方で死亡退院者は、年間約2万人程度いるため、10年の間に約20万人以上の入れかわりがあることになる。それでも、一向に長期在院の問題が解消されていないということは、出口の問題というよりは非自発的入院問題をはじめとする入口にこそ問題があると考えられなければならない。医療基本法の制定が進み、患者の権利のための改革がおこなわれれば、患者の権利の観点から非自発的入院をはじめとする入口が見なおされ、長期在院問題の解消にもつながる。
5.2 入院処遇に起因する心的外傷及び副作用被害の縮小
この間に精神科における身体拘束は、10年で2倍以上にまで増えた。隔離も増加の一途をたどっている。通信面会も制限される傾向にあり、家族以外の面会を認めないとする病院もきわめて多い。精神科病院の問題はいろいろ指摘されているが、患者らは院内の雰囲気(看護師の態度や処遇)が悪いということを必ずいう。そして、その延長線上には虐待や死亡事案がある。先に述べた37条1項大臣基準は、一部の行動制限について手続きを定めてはいるものの現場では、手続きさえ守れば何をしてもいいといった状態である。こうした状況に対して医療基本法の制定を進めることで、実効性のある患者の視点にたったものに変わっていければ処遇の改善につながり、それをもって患者らの被害の縮小になると考える。
6 報告書に示された内容からみて、当事者、国あるいは自治体、医療の現場などは、どういう状態にあると捉えておられますか。
6.1 疾病を理由とする差別・偏見の克服
疾病を理由とする差別・偏見の克服については、後退していると判断する。
第193回通常国会内閣総理大臣施政方針演説では、「昨年七月、障害者施設で何の罪もない多くの方々の命が奪われました。決してあってはならない事件であり、断じて許せません。精神保健福祉法を改正し、措置入院患者に対して退院後も支援を継続する仕組みを設けるなど、再発防止対策をしっかりと講じてまいります。」として、措置入院患者に対する退院後支援の仕組みを設けることが、犯罪の再発防止策になるかのように述べられている。これは精神障害と犯罪を安直に結び付けた差別・偏見に依拠したものであるが、首相が発言するほど社会に根付いてしまっているという点では、克服までの道のりは相当に険しいと言わざるを得ない。
これまでライシャワー事件、西口バス放火事件、池田小学校事件と事件のたびに容疑者の精神科受診歴と事件を結びつける対策が講じられてきた。相模原事件も例外ではなく、事件と容疑者の措置入院歴がクローズアップされて、再発防止策として措置入院の見直しの検討がおこなわれたものである。事件と法改正が文脈的にも結び付けられてしまっている状態は、精神障害者を危険とみなす考え方を促進し、偏見を助長するものと考える。こうした精神障害者を危険とみなす考え方によって精神障害者とそうでない者との間に差別と分断を生じさせ、共に生きる社会に逆行した考え方を推し進めていくことになるのではないかと深刻に憂慮する。
6.2 正しい医学的知識の普及・啓発及び人権教育の徹底
正しい医学的知識の普及・啓発については、後退していると判断する。
報告書においては、正しい知識を普及、発信する主体に患者が含まれているかどうかが不明である。というのは、序文には、「被害当事者から学ぶことが必要」とされているが、各論の「Ⅱ 正しい医学的知識の普及・啓発」の部分には発信主体に患者が含まれていないのである。これは、患者の役割が差別・偏見の克服と人権教育に限られ、正しい医学的知識の普及・啓発においては期待されていないとも読めなくはない。しかし、精神医療においては、製薬資本の影響を受けて生物主義の研究が取りくまれ新薬が頻繁に開発されても成果があがっていないため、医療従事者らは限界を感じて当事者の取り組みを参照した知識の普及をし始めた。その知識も不正確で危ういものが散見されるため、患者は、差別のことだけではなく、医療のことも発信していく必要性に迫られている。
人権教育の徹底については、後退していると判断する。被害当事者から学ぶという取り組みが医学部教育などでカリキュラム化されておらず、例えば障害学など本人目線の科目をおいている大学自体がほとんどない。
6.3 施策を推進するための組織・機関の設置
施策を推進するための組織・機関の設置については、後退していると判断する。序文にも書かれているパリ原則に基づく国内監視機関は、規約人権委員会の総括所見をうけて一時期、設置の機運が高まったが、その機運も今では見る影もない。
7 報告書の内容と現場の実態に乖離した部分があれば、その具体的内容についてご教示ください。
上述で後退と評価したものは、必然的に報告書と実態の乖離を帰結する。とりわけて著しい乖離を感じるのは、相模原事件の再発防止の検討を通じて精神保健福祉法の措置入院が見直されたことである。現在、精神保健福祉法改正法案は廃案となったが、同じような法案が上程される見込みであり、報告書の内容と照らして著しく実態が乖離している。
8 その現状をふまえ、差別・偏見の克服に向けて、次のステップとして、具体的にどのような取り組みが必要と思われますか。
8.1 非自発的入院及び行動制限の廃止に向けた検討の開始
差別・偏見の克服に向けては、精神保健福祉法改正法案が上程見送り、もしくは上程後に廃案となり、再検討の上で出し直される必要がある。また、出し直しにあたっては、障害者権利条約政府審査に基づく障害者権利委員会総括所見を反映させるための検討の場を明文で規定する必要がある。こうすることで、次の見直しでは精神障害を理由とした非自発的入院及び行動制限の完全廃止に向けた議論を開始することができ、差別・偏見の克服に向かうことができる。
8.2 障害者差別解消法の見直し
障害者差別解消法を見直し、合理的配慮の提供を民間事業者へも義務化し、裁判規範性のある法律にする。より多くの人が障害者との接点をもち配慮を考究することで、差別・偏見の克服につなげる。
8.3 障害者虐待防止法の通報義務の対象に精神科病院を入れること
障害者虐待防止法を見直し、通報義務の対象に精神科病院を入れることで、精神科病院内の閉鎖的体質に変更が加わり、差別・偏見の克服につながる。
8.4 精神障害者の地域生活の確立
障害者総合支援法の見直しを通じて、重度訪問介護の利用拡大や精神障害者にとって使いやすい介護にしていく必要がある。精神障害者の長期在院が解消され、地域生活が進めば、地域における精神障害者との接点が増えることで差別・偏見の克服につながる。
8.5 多様で実効性のある権利擁護システムの確立
上述の仕組みは、権利擁護の側面を有するが、より実効性のある権利擁護システムの確立が不可欠である。具体的には、孤立して入院している者とのつながりをつくり、地域生活を可能としていくための訪問活動などがそうである。こうした取り組みを通じて、精神障害者の長期在院が解消され、地域生活が進めば、地域における精神障害者との接点が増えることで差別・偏見の克服につながる。
8.6 患者団体への経済的支援
差別・偏見の克服にあたって患者団体の果たす役割は大きいが、その経済的な基盤が医療従事者職能組織と比べて非常に脆弱であり、活動をしていくための経済的な裏付けが必要である。
9 差別・偏見の克服に向けた取り組みにあたり、障害となる要因はありますか。あるとすれば、その具体的内容をご教示ください。
9.1 精神障害者の政策過程からの参画が進んでいないこと
差別・偏見の克服に向けた取り組みにあたり精神障害者の政策過程からの参画が進んでいないことは、患者目線を政策に反映できない点で第一の障害となる。
9.2 精神保健福祉法改正法案
相模原事件の再発防止の検討を通じて精神保健福祉法の措置入院が見直され、精神保健福祉法改正法案として上程されることが見込まれている。こうした法案が上程見送り、もしくは上程後に廃案となり、再検討の上で出し直されなければ差別・偏見の克服は難しいと考える。また、出し直す理由も、精神障害を理由とした非自発的入院及び行動制限の廃止を検討するためのものでなければならない。
9.3 医療観察法
犯罪行為を医療によって治すという医療観察法も、立法レベルで精神障害者に対して差別・偏見を有しているため、廃止されなければ差別・偏見の克服は難しいと考える。
10 差別・偏見の克服のための一定の制度化が進んだ場合、実際に、医療の現場(患者の生活)にどのような影響がある、あるいはどのような変化が起きると思われますか。
現状のままでは、差別・偏見の克服はきわめて困難であるが、時間をかけて取り組みを重ねることで医療現場にも徐々に変化がみられるのではないかと考える。